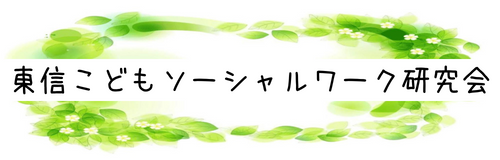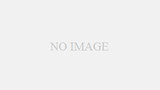9月に続きAさん(40代女性)から〈身体はトラウマを記録する〉の感想文が届きました
〈“自信に満ちた有能な親になるには、頼りになって、反応が予測できる親の下で育つ
こと” これはすごいことだと思った! こういう親がいいなって思った!〉
「身体はトラウマを記録する」(ベッセル・コーク著・杉山登志郎解説・紀伊国屋書店
・2016刊)を p.510 まで読みました。長い道のりで~す。あと150ページ。
〇 「赤ん坊の頃に安心感が得られなかった子どもは、成長しても気分や情動的反応を調整するのに苦労する。幼稚園では、多くの無秩序型の幼児が攻撃的か、ぼうっとして人や物事に関与することをやめてしまっているかのどちらかで、やがてさまざまな精神医学的問題を引き起こす。この種の生物学的調整不全は、子どもが成熟したり、安全な環境に移されたりすると、自動的に正常な状態に戻るだろうか。私たちの知る限りでは、そうはならない。」(p.194)
自分自身のトラウマで頭がいっぱいの親は、情緒が不安定で子育てに一貫性がありません。子どもに同調できない。私の親も同じ状態でした。
〇 「不快な出来事に対する子どもの反応は、親がどれだけ平静か、あるいはどれだけストレスが溜まっているかでおおむね決まる。」(p.196)
要はそういうことなんだなーって。他者にひどい扱いを受けるのは当たり前だと思い始めるのは、これは無意識です。自分では自覚できない。
あと危険と安全が判断できない。いつも緊張していたり、あるいは危険を正しく認識できなかったりする。
〇 「私たちは子どものころ、自分自身の宇宙の中心として人生を歩み始め、あらゆる出来事を自己中心な視点から解釈する。親や祖父母が、お前は世界で一番かわいいと言い続ければ、まさにその通りに違いないと思い込む。
その結果、のちにつきあっている人にひどい扱いを受けると激怒する。
だが、子ども時代に虐待されたり無視されたり、あるいは性的な事柄が嫌悪に満ちた扱いを受ける家庭に育ったりすると、心の中の地図は、それとは異なるメッセージを含むことになる。私たちは軽蔑や屈辱を特徴とする自己感覚を抱くようになり、“あの人の方が一枚上手だ”と考えて、虐待されても抵抗できない可能性が高い」(p.211-212)
子ども時代にネグレクトや敵視や、大事にされないとそうなります。
私が実家へ帰ってきたとき、子どもがわたしにパンチ?して来たのを見て母は子どもに“なんでそんなことするの!”と言った。
私が小さい時、母はあんなに私を虐げたのに! 私はいつも順位が一番下でした。 死んでもいい人間、いなくてもいい人間でした。
このごろ母にそのことを確認したら、“無意識だった”と。
〇 「子どもは、自分の家庭の中で生き延びられるように自分を組み立てるより他に選択肢がない。彼らは大人とは違い、外部の権威に頼って助けを求めることができない。親こそが絶対的な権威なのだ」(p.220)
命に関わるくらいなら、もしかしたら児童相談所が助けてくれるかもしれない。
でも、家に変なルールがあったり、罰でご飯がもらえなかあったり、叩かれたり、ちょっとした嫌がらせを長期的にやられたりするくらいでは、助けてもらえない。
頑張って勉強して、大学まで出て、自立して逃亡するしかない。
〇 「カリフォルニア州の囚人の7割は、児童期に里親のもとで暮らした経験がある。
ヨーロッパ北部の国々では、親が安定した環境で子どもを育てられるように投資している。彼らの学力検査の得点と犯罪率は、こうした投資の成功を反映しているように見える」(p.280)
日本もこうなってほしい。今 虐待されている子、たくさんいます。強い暴力全般だけじゃなく、子どもにとってしんどい生活全般です。
ヤングケアラーの問題もそうです。私の友人は小さいころ、認知症の祖父の面倒を看ていて、時に殴られたそうです。
とにかく、子どもたちが安心安全で成長できるように、周りは努力していきたい!
〇 「だが、確実に分かっていることがある。自信に満ちた親になるためには、頼りになって、反応が予測できる親の下で育つことが大きな助けになる。あなたのことが大好きで、あなたの発見や探索に喜びを見出す親、あなたが責任ある行動を取れるようになることを助けてくれる親、あなたが自立し、他の人とうまくやっていくうえで手本となってくれる親の下で育つことが」(p.506)
父親はこういう部分があったけど、母親にはなかった。
ただ、私が生きていくうえでラッキーだったことは、他人との出会いにすごく恵まれていたこと。先生や医療関係の人々。“死にたいなー”と思うことがあっても、出産の時にすべてをかけて命を救ってくれたスタッフの皆さんのことを思うと、生きなくちゃ!って思う。
私の負の連鎖は止まったのでしょうか?
私って愛情が薄かったなと何となく思っていたのですが、気づかせてくれたのは下の子です。ありがとう。
大学に進んだ上の子は、ほぼ一人で頑張って進学しました。頑張ってやってますきっと、上の子的には不満だったでしょう・・・?
◆ 田中から応答しました。 ~Aさんの負の連鎖は止まりつつあるみたいですね~
● “負の連鎖”は止まりつつあると思います。
母親に昔のことを確認したら、“無意識だった”と言われたとのこと。
そういう妻を受けとめ続けて来た父親がいます。すごい人だと思います。
下の子から教えられたとのこと。
上の子は“不満”より、分岐点できちんと選択できたことに満足していると思います。あなたを乗り越えたように感じます。
● この本は p.674 ある厚い本です。こうして自分と家族のことを振り返りながら読み進めていることが、素晴らしいです。成長を感じます。
残り僅かになってきました。感想文を待っています。
● “大学まで出て、逃亡するしかない”
「逃亡」という言葉が引っかかりました。
虐待を受けて子どもたちには、必ず〈分岐点〉が来ます。
どちらの道を選択するのか?
的確な選択ができるよう、向かい合っているつもりです。
また、あなたの父親は逃げずに寄り添い続けて来たように感じます……。
SWの世界では、“パンドラの箱を開けるときは覚悟が必要”と言われています。
● “生物学的調整不全は、子どもが成熟したりすると、自動的に正常な状態に戻るだろうか? そうはならない。”
ここで立ち止まっている、困っている子どもたちがいます。先生など支援者もどうしていいのか分からないケースが、多いと思います。
初めは、1対1の関りで、〈愛情を支援する〉ことが必要です。欠けているのは、愛情と言う子どもが多いのです。(愛着形成)
子ども自身が自分で気持ちを切りかえるには、アタッチメント(愛着)の内在化が必要です。
一貫性と規則性を持って関わること。会えない時間の期待感が想像力を高め、その内在化を準備・促進します。
End.