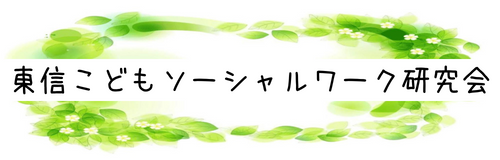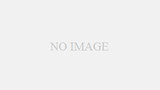《今は、小さな幸せがすごいです。自由に生きてます。下の子は私にいっぱい甘えてきます。私は大丈夫です。(笑)》
いつもの40代女性・Aさんからメールが届きました。
〇父から日曜日の信毎に掲載されている「発達障がい」の記事が届きます。
その中に、“暴力をふるっちゃって、仕事 首になった”とありました。
私も小中でいきなり友人とか後輩を引っぱたいて、泣かしたことがあった。
学校は発達障がいの子になかなか適切に関われないと思う。理解できないって思う。
父にも実感としては分かってもらえないだろう…?
でも父はとても楽観的な人です。母親もそうだったと言ってます。
母のことでしっくりくる言葉と言えば、他人行儀。私のこと他人と思っている。
自分の思うように生きようと思う気持ち 対 自分を無意識に抑えて、押し殺して生きてしまう(惰性)。
私の後ろにいる両親が、私の心の中で戦ってる感じ。揺れてますね。
〇“いきなり引っぱたいた”のは、故意ではないです。
友人からは、殴ることないじゃん! と言われました。
このことが問題になることはなかったし、先生が入ることもなかったです。
ただ嫌われただけになりました。体罰が当たり前の時代でした。
グレーゾーンの子も放っとかれましたね。
子どもの担任の先生は、私からこうしてほしいと言える先生でした。こどもは一人でいる時間を確保してもらいました。
〇“学校が適切に関われない”は、表面的なものは見えるけど、深い所にあるいろいろな問題や感覚や世界観は、学校や社会では見えない気がする。
子どもの感覚過敏をうけ止めてくれた担任の先生には、いろいろ相談しました。
過敏だったり、どうにもならない睡眠障がいとか、衝動的だったり、あの常に揺れてるってのは、それが一番落ち着くからなんです。多分……。私個人はそうです。
その上で、二次障害として「うつ」とか「そううつ」が出てきます。
〇“社会に絶望しないためには”グループを強固にすることかな……。
DVや摂食障害などの自助グループのようなつながりは凄くありがたい。
別に解決するわけじゃないけど、居心地がいい。
先日はNHKで、トランスジェンダーの会をやってました。体験を共有するって大事。
〇“母は私に他人行儀”は、母の両親らとの関わりから、そうなったと思う。
両親からのネグレクトや親族からの暴力が、あったみたい……。
だから、母は自分の子どもとどう関わっていいのか、分からなかった……。
下の子は私にいっぱい甘えてきます。(笑)私は大丈夫です。(笑)
〇“揺れてるって”とはどういう状態かと言うと、こうなりたい・できていない・できないなあ、で揺れている・・・。
昔ある講座に参加した時のノートには、“我慢ばかり”じゃなく、自分を出せるようになりたい。意見をちゃんと言えたり、自信が持てるようになりたい。と書いてました。
〇“父が信毎記事を渡してくれた”のは、数年前父に発達障がいをカミングアウトしたからです。“私はポンコツだよ”と付けくわえました。
その記事を読んだら少しだけ具合悪くなりました。
“無理やり集団になじませようとされて、そして中学で不登校になり、その過去を思い出すと、苦しいから死にたくなる”という記事です。
私は、小学校で先生に恵まれました!
今は、小さな幸せがすごいです。自由に生きてます。
田中からの応答 “人の嫌がることを言わない・しない・許さない”から始める。
・Aさんの“心の中で戦っている感じ。揺れてますね”と聞いて、揺れるって大事なことだと感じました。
揺れて、揺れて、そして今は“ちいさな幸せ”をつかみ取ったみたいです……。
Aさんのお父さんは、楽観的だったからお母さんと結婚したと思います。
そして、Aさんが実家へ帰って来ることを歓迎してくれた、居場所にいます。
・人は恐怖やショックが重なると、凍りつき・固まり・ひどく眠くなったりします。
「身体はトラウマを記録する」(ベッセル・コーク著、柴田博之訳・2016刊)の“第13章・トラウマからの回復-自己を支配する”には、“トラウマは自分を取り仕切っているという感覚を人から奪う。回復のための課題は、体と心、すなわち自己の所有権を取り戻すことだ。それは圧倒されたり、激怒したり、恥じ入ったり、虚脱状態に陥ったりせずに、遠慮なく自分が知っていることを知り、感じているものを感じるということだ。”と述べています。
他人に支配されるのではなく、自己を支配する。
Aさんは今、“ちいさな幸せ、いっぱい&自由に生きてます”と言えるようになった!
・Aさんの衝動的な友人たちへの暴力は、母親の生い立ちを聞くと、その影響が強いように感じます。愛着形成が行われなかったことの影響が。
Aさん自身の問題は、自閉症というより、愛着形成・親の生育環境などの影響が大きいと感じてきました。
子どもがいっぱい甘える&甘えさせる Aさんになったことが、嬉しい!
・「タフラブ 絆を手放す生き方」(信田さよ子著・2022刊)に、どのような関係を作っていくかがカギとなる! と書かれてありました。(p.206)
“私が一番嫌いなことばが、〈自分を好きになりましょう〉〈自己肯定感を高めましょう〉である。〈専門家〉と呼ばれる人たちが、〈自分を愛せない人が、他人を愛せるはずがありません〉と語ることがあるが、そんなことはない。
むしろ、一番大切な人、仲良くなりたい人、もしくは身近でうとましく思う人とどのような関係をつくっていくかが「カギ」になる。”
・私が作っている関係は、大切な人を身近な円の中に置きます。仲良くなりたい人は少し離れた円の中に置きます。うとましく思う人は遠く離れたところに置き、にこやかな挨拶だけは欠かしません。
対人支援の仕事をして15年。誰とも喧嘩したことはないと言うと、皆さんから驚かれます。フツウだと思うけどな……。
・イジメの影響って、長く続きます。
だから、保育園・幼稚園から「人の嫌がることを言わない・しない・許さない」がとても大事だと思います。〈私は〉を主語にして!
学校などでそれが当たり前になっていれば、人と社会へのマイナス・イメージを持たなくて済むと思います。
振り返りすることが大事です。絶望ではなく、希望を感じるために……。
End.